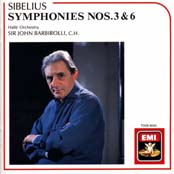
|
シベリウス 交響曲 第3番 ハ長調 作品52 交響曲 第6番 ニ短調 作品104 サー・ジョン・バルビローリ 指揮 ハレ管弦楽団 (V/1969, V/1970) |
雪のカラマツ林の中でただ独り佇む。林の中はどこまでも明るく,空気は冷たく澄んでいる。そんな静寂の中で,目を閉じてみると,どこかで音楽が鳴っているように感じられてくる。そんなとき聞こえてくるのは決まってシベリウスの第6交響曲だ。日常生活で孤独になるのは簡単なことだが,ひとり冬の森の中に入っていっても,不思議と寂しさは感じないものだ。頭の中は澄み渡り,時間も思考も限りなく静止に近づいていく。雪を被った峰々をながめる季節が巡ってくる度に,森の中に入って行きたくなる誘惑に駆られる。そんなときは第6交響曲を聴いて,若かりし頃に歩き回った,蓼科のカラマツ林をしばし懐かしむことにしている。
第6交響曲を初めて聴いたのは中学生のときだ。ラジカセでNHK-FM放送をかけながら,自分の部屋から何気なく外の風景を眺めていた。そのとき流れてきたのが,渡辺暁雄指揮日本フィルハーモニー交響楽団の演奏だった。たまたまカセットにそのときの放送を録音していたのだが,それ以後,音質は悪かったにも関わらず,彼らの演奏が,私にとってのシベリウスのスタンダードになった。それから四半世紀以上にわたって,シベリウスの音楽を聴き続けている。私の人生の喜怒哀楽とは,まったくかけ離れたところに超然とその音楽は「ある」。その音楽は私を打ちのめしもしないし,私の気持ちを鼓舞したりもしない。だからとてもありがたい。これからもシベリウスの音楽を聴き続けていくのだと思う。
基本的にテンポの変化を好まない私だが,バルビローリは別格。私は彼のシベリウス,マーラー,ブラームスを愛する。彼の演奏を聴いて,音楽を聴ける幸せを噛みしめる。とてもありがたいことだ。
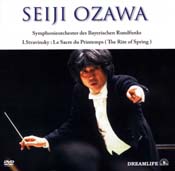
|
ストラヴィンスキー バレエ音楽『春の祭典』(1947年改訂版) 小澤 征爾 指揮 バイエルン放送交響楽団 (VI/1983) |
今月はCDではなくてDVDの紹介。1983年6月17日にミュンヘンのヘルクレスザールで開かれた,バイエルン放送交響楽団のコンサートライブ映像である。シェーンベルク『グレの歌』やマーラー交響曲第8番『千人の交響曲』などの大曲を次々と録音し,小澤征爾が絶好調であった40代後半の演奏であり,まさに天才の記録と呼べるようなものだと思う。素人の私から見ても,指揮振りは明確そのもの。複雑極まりないこの曲の練習にあたっても,すべて暗譜でこなしていたという日本のオケマンの証言があるが,この映像を見ると,この曲の複雑なリズムがすっかり彼の体に染み込んでいることがわかる。
彼にはアメリカの交響楽団と録音した2種類のレコードが既にあるが,演奏内容はこのDVDがベストだと思われる。シカゴ交響楽団やボストン交響楽団との演奏では,オケの機能に任せて,リズムが前のめりに先走っているようなところが見られるが,このDVDではそのような不安定感は見られない。テンポの落ち着きと深い音色は,ドイツの名門オケの面目躍如といったところだろう。またオケのメンバーが,小澤の棒に全面的な信頼を寄せている様子は,映像からも一目瞭然だ。(この曲が日本で初演された際,オケの演奏が終わったのに指揮者は棒を振り続けていたという。)
DVDではCDとは違った楽しみ方ができるのも嬉しい。管楽器の持ち替えの多さも見ていて楽しいし,この曲の独特な音色を支えているアルトフルートの役割も一目瞭然だ。複雑なリズムをこなすパーカッション群の活躍,さまざまな金管楽器が繰り出す神業など,一流オーケストラの演奏の醍醐味を映像でたっぷり味わうことができる。ウィーンフィルのニューイヤーコンサートのライブも良いが,私にとっては,こういった曲の方がお買い得感があるかも。

|
ブラームス ピアノ協奏曲 第1番 ニ短調 作品15 マウリツィオ・ポリーニ (Pf) カール・ベーム 指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (XII/1979) |
この曲がなぜ好きなのか?たぶんブラームスの「若気のいたり」が顔を覗かせているところだと思う。作曲にはまるまる2年間を費やしているし,「若書き」などといってはブラームスに失礼だとは思うが,曲の冒頭から前のめりに進行していく様は,後年の慎重居士ブラームスの音楽とは大分趣を異にしていて微笑を禁じ得ない。あふれ出てくる若いエネルギーのやり場に困って,自分でも持て余して葛藤している姿。この曲は,そんな青春時代が,20代のブラームスにも存在していた証になっている。
自分が恋している女性に夫がいたらどうするか?しかもその夫が,自分の尊敬してやまない人物であったとしたら。さらに,その夫が鬼籍に入ってしまったとしたら……。作曲当時,ブラームスが置かれていた状況は,まさにそんなところ。シューマン夫妻への想いを,深く窺い知ることはできないが,結果として,ブラームスは一生独身を貫き通した。「オペラを書くくらいなら,結婚した方がマシ」という言葉も残っているが,果たしてどのような心境で述べたものなのか。
ポリーニの弾くブラームスはメリハリが利いていて明晰で好感がもてる。イタリア弦楽四重奏団との「ピアノ五重奏曲」でも同様。晩年のベームの指揮ぶりは,よれよれのことも多かったようだが,このCDでは引き締まっていて推進力がある。独奏者のポリーニとウィーンフィルのコンサートマスター,ヘッツェルによるところが大なのだろう。
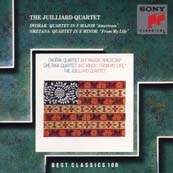
|
ドヴォルザーク 弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 『アメリカ』 スメタナ 弦楽四重奏曲 第1番 ホ短調 『わが生涯より』 ジュリアード弦楽四重奏団 (XII/1967, I/1968) |
誰のどんな趣味にも,「入門するきっかけ」というものが存在するということは自明であろう。しかし,それだけでは不十分で,趣味としてのめり込み,次第に深みにはまっていくためには,別のトリガーというか契機というか,そんなものも必要である。このCD(中学生当時はLPレコード)は,私にとってそんな1枚だ。この演奏で,私は室内楽を聴く愉しみを初めて知ったし,また,クラシック音楽というジャンルの拡がり,奥行きといったものを初めて実感した。
60年代のジュリアード弦楽四重奏団はすごかった。すぐに名前があがってくるのは 1st Vn のロバート・マンであるが,他の3名も腕っこき揃いである。ドヴォルザークもスメタナも,ビオラの主題提示で始まるが,ラファエル・ヒリヤーが奏でる,その旋律の雄弁で,その音のボディのしっかりしていることといったら,聴く度に感銘を受ける。特に,スメタナの開始における,緊迫感とシリアスさは比類がないように思える。
ジュリアード弦楽四重奏団に代表される現代的な演奏スタイルは,お国もの,ヨーロッパ優先の日本では,評判が今ひとつのようである。しかし,各声部が対等で,音楽の構造をちゃんと聴き手に伝えてくれるという点で,私は安心して,そのしっかりした音響に浸っていることができる。クリーヴランド弦楽四重奏団による『ベートーヴェン弦楽四重奏曲全集』などとともに,いつも傍らに置いておきたいCDである。
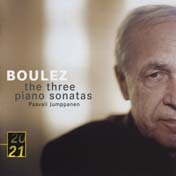
|
ブーレーズ ピアノソナタ第1番, 第2番 & 第3番 パーヴァリ・ユンパネン (Pf) (6-7/2004) |
「オペラ座を爆破せよ」「シェーンベルクは死んだ」など,若いときの過激な発言も含めて,作曲界の先頭に立ち続けてきたブーレーズも,今年(2005年)で齢80である。彼の傑作『ル・マルトー・サン・メートル(主のない槌)』が初演されたのは1955年であるが,この年を軸に,第1ピアノソナタ(1946),第2ピアノソナタ(1947-48),第3ピアノソナタ(1955-57)と,作曲年を知っておくと作品理解の手助けにもなるであろう。
このCDの第2ソナタを聴いたとき,少なからず驚いてしまった。何に対してか?普通に解釈して演奏しているユンパネンと,それを平然と楽しんでいる自分に対してである。初めてこの曲を聴いたのは,おそらく大学生のときで,かなり背伸びをしていたと思われる。ポリーニのLPレコードだったのだが,たいへん気負った気合いの入った演奏であった。第1楽章の出だしから「これから(文化的な)大事件が起こるんだ」といった雰囲気が,聴き手にも伝わってくるような演奏であった。それに比べてこのユンパネンはどうであろう。全ての力感は整理され,ブーレーズが仕掛けた,様々な音列による構造がさりげなく浮き彫りにされている。ポリーニにとっては同時代の生々しい音楽が,ユンパネンの手によって,完全に古典という枠内に押し込められてしまったという印象である。
第3ソナタはジョン・ケージの影響を受け,「管理された偶然性」がテーマとなっている。ブーレーズは以下に紹介するコメントのように,ユンパネンの演奏に肯定的だが,そこにフーコーがいうところの「管理のまなざし」と「権力の構造」を感じてしまうのは私だけ?
「パーヴァリ・ユンパネンは,この3つのソナタを理解する力と,演奏出来る技巧をそなえている−−とくに第2番はきわめて難しい曲だ。そして彼の第3番の解釈は,真にその迷宮を理解したことを示している。私は,自分とはちがう時代に育った奏者がどのようにこれらの作品を捉えるのか,興味があった。私にとってこれらの作品は自分の発展の段階を示すものであり,自分自身の一部でもある。彼にとってこれらの作品は,彼が人生の中で見つけ,それに関わり,何か意味を与えねばならない対象物なのだ。」--- ピエール・ブーレーズ ---
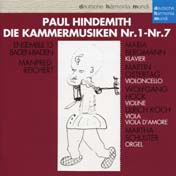
|
ヒンデミット 室内音楽集 第1番--第7番 (全曲) マリア・ベルグマン (Pf) ウルリヒ・コッホ (Va) マルタ・シュースター (Org) マルティン・オステルターク (Vc) ヴォルフガング・ホック (Vn) マンフレート・ライヒェルト 指揮 バーデン=バーデン合奏団 (12/1977--3/1978) |
J.S.バッハ,C.P.E.バッハ,テレマン,ヘンデル,ヴィヴァルディ...etc,様々なスタイルの合奏形態に出会えるのも,バロック音楽を聴く愉しみのひとつだ。特にバロック期の協奏曲は,一口に協奏曲とはいっても,コンサートで演奏されることを前提とした後世のそれとは違って,ソロ楽器も編成も多様性に富んでいて,奏楽の愉しみにあふれている。
ヒンデミットはKammermusikというタイトルをつけているが,ここでのKammerとは,王侯貴族の宮殿ないし館を指していて,コンサートホールで演奏される室内楽でもなければ,市民の家庭音楽Hausmusikとも異なるものだ。バロック的な奏楽の愉しみや即興的な感興を20世紀に持ち込んだらどうなるか。ヒンデミットの作曲動機はこんなところにあったのではないか。
ヒンデミットは音の才人であり教養人でもあった。これらの曲を聴いていると,知識人としての自負と,それ故の危うさが感じられてならない。(ジャケットの自画像にも,彼の屈折を読み取ってしまうのは,私の思い過ごし?)R.シュトラウスに代表される懐古的な後期ロマン派の人気にも媚びず,シェーンベルクら無調音楽から十二音音楽へのムーブメントにも距離を置き,明晰な知性と高い教養に支えられ,音楽と戯れた。そんな彼の目には,ナチスの台頭を支えている大衆が,どのように映ったことであろうか。
このCDの演奏はヒンデミットの初期の意図を忠実に伝えてくれていると思う。アバドやシャイーの演奏の方が,その音響はゴージャスだけど,なにか大切なものが欠落しているように感じられる。このCD,もともとはテイチクからLP3枚で発売されていたもので,学生時代から私の愛聴盤であった。何故にテイチク?そこら辺の事情は知らない。
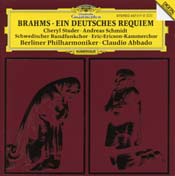
|
ブラームス
『ドイツレクイエム』 シェリル・ステューダー (Sp) アンドレアス・シュミット (Br) スウェーデン放送合唱団 エリック=エリクソン室内合唱団 クラウディオ・アバド指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 他 (10/1992) |
自分の心を見つめるとき,内なる声に耳を澄ますとき,何度この曲を聴いたことだろう。
この曲を初めて聴いたのは,明治学院大学のチャペルで,その大学の合唱団の演奏会だった。高校1年生のとき,2年生の先輩に連れて行ってもらったっけ。同じクラスの女の子も一緒だったはずだけど,なぜか彼女のことはあまり印象に残っていない。それだけ,この曲の印象が強烈だったからだろう。先輩は,当日の演奏をあまり褒めていたかったけど,私がこの曲にのめり込むには十分な演奏内容だったと思う。
この曲はルター訳マタイ福音書5:4の有名な一節で始まる。Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getrostet werden. 透き通った合唱でSelig sindと何度も繰り返され,その響きに身も心も浸しきる。若いときは,この一節に音楽的な美しさしか感じられなかったけれど,年を重ねるごとに失うものも増えてきて,その意味が深く胸に染み込んでくる。全曲のクライマックスは第3楽章終盤のフーガだと思うが,演奏がここに至る度に,自分という人間の小ささを思う。
このCDは合唱がとても美しい。アバドはカラヤン亡き後のベルリン・フィルを引き継いで,メンバーの世代交代という難しい時期に首席指揮者の任にあった。カラヤン時代に比べて,オケの音響は軽くなったものの,音の透明感は増して,この曲に関して云えば,合唱の透明感と相まって,美しい演奏の実現に成功していると思う。
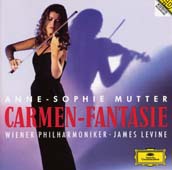
|
サラサーテ
『ツィゴイネルワイゼン』
『カルメン幻想曲』 ラヴェル 『ツィガーヌ』 マスネ 『《タイス》瞑想曲』 他 アンネ=ゾフィー・ムター (Vn) ジェイムス・レヴァイン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (11/1992) |
この人の凄いところは,ヴィヴァルディだろうがベートーヴェンだろうが,どんな曲でも自分の方にグイと引き寄せてしまうことだと思う。昨年は「オレ流」という言葉が流行ったが,まさにそんな言葉がぴったりだ。太く,たっぷりと,ロマンティックに朗々と歌いながらも,決して下品になることがない。果物は腐りかけが一番美味しいと云われるが,まさにそんな感じ。それでいて奏でられる音は一定の気品を保っていて,堕落することがない。希有な才能なのだと思う。
レコードデビューは,14歳のとき,カラヤン&BPOとだった。このレコードが日本で発売になったとき,私は中学校に上がるか上がらないかくらいで,「世界には凄い女の子がいるもんだ」と思ったものである。その後のキャリアの中で,ジュリアードなどのメジャーな音楽院と全く関わりを持たなかったせいか,変に個性を摩耗させることもなく,ヴァイオリン界の女王にのぼりつめてしまった。「ジュリアード出のバイオリン奏者は額に見えない印をつけている」とは彼女の言。こんな発言が許されてしまうのも,超一流の証であろう。
勝手放題な演奏をしているようで,実は共演者(特に指揮者)のコンセプトにも柔軟に対応しているようだ。同じ『ツィゴイネルワイゼン』でも,小澤征爾との共演では清清楚楚とした演奏を展開しているし,バルトークの協奏曲(第2番)でも,朗々と歌いながらも,小澤の枠にぴったりと寄り添っている。ただし,このCD,レヴァインが「好き放題やってちょうだい」というスタンスでいるのか,ムターはやりたい放題である。演奏の精度より音楽の勢い重視。ウィーン・フィルの伴奏も同様。このレヴァインっていう人,三大テノールの伴奏を買って出たりして,たまに何を考えているのか分からないところがある。捉えどころの難しい,彼のマーラーに接したのも,もう25年近い昔の話になってしまった。



