製造業の利益
1997 福永
- 資本主義社会の企業活動の目的は投資された資本に対して利益を確保する事である。製造業の場合は製品の販売先を確保し、その売上の結果から営業利益を引き出す。
- 1997年の業績報告を東洋経済新報社の「会社四季報」の CD-ROM から製造業の上場企業等(店頭銘柄および管理銘柄を含め)の約1600社について調べてみると、売上高と営業利益の間の関係は次の図に示されるようなものである。
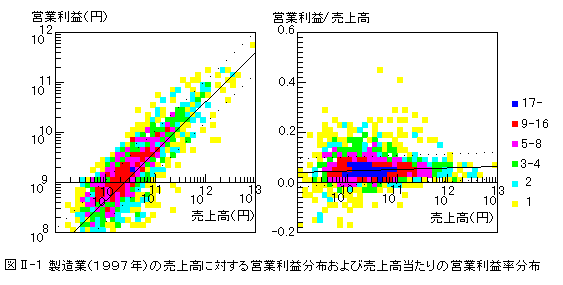
- 売上高に対する営業利益の比は右肩上がりであり、平均値は約 4.5% であり、売上高の一桁の増加に対して約 1.3% の増加を示す。標準偏差は平均値を 1 としたとき 1.19 と大きく、企業は平均値の周りに -0.19 から 2.19 倍の範囲に散らばっている。この年度の企業活動はかなり多くの企業がマイナスの営業利益を出したことを示している。
- では企業の固定資産に対する営業利益、および従業員に支払われた年間総賃金と営業利益との関係はどうなっているであろうか?次の図はこれらの間の関係について示す。
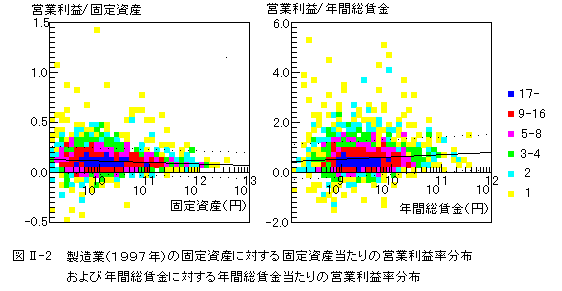
- 営業利益の固定資産に対する割合の分布は右肩下がりであり、年間総賃金に対する割合は右肩上がりである。生産設備が増えるにつれて利益率は減少するが、従業員数は大きいほど利益率は増加すると読むべきであろう。
- 一般的に、営業利益は企業の経済活動の目的ではあるが、それは製品の販売の結果として得られるものであり、幾つかの要素の引き算の結果として求められている。それは基本的には次のようなものである。
- 営業利益=売上高ー販売・管理経費ー売上原価 (1)
- 売上原価には人件費即ち従業員に支払われる年間総賃金と原材料費等(通常の意味での原材料費の他に施設・設備の維持・運転経費やエネルギー代・消耗品費を含む)が含まれる。
- 原材料費等と人件費(年間総賃金)を合わせたものは製品を生産するために必要な費用即ち原価である。売上高と売上原価との間の関係を示すのがつぎの図である。
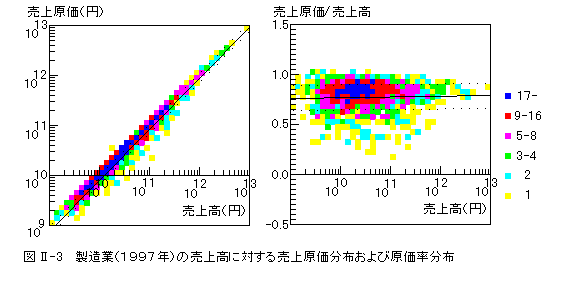
- この両者、即ち、売上高と売上原価との間には強い相関が見られる。原材料費等と年間総賃金に見られたばらつきの大きさ、即ち標準偏差の大きさは両者を加えたものである売上原価では、それぞれのばらつきが相殺されているようであり、その上に売上高の規模の大きさに対する変化も相殺されてより水平化されている。これらのことに見られるのは、企業活動にとって従業員数と原材料費等は相互にはそれほど強い相関のある量ではないのに、両者を加えたものは企業の経済活動にとって重要な量として、何らかの強制があると見るべきであろう。
- 次の図4には、この売上原価に対する営業利益率の分布、および資本金に対する営業利益率の分布を示す。営業利益自体が大きなばらつきのある量であるために、原価に対してもまた資本金に対しても、利益率には大きなばらつきを持ち込んでいる事がわかる。両者ではともに右肩下がり、即ち売上原価の大きな企業の場合も、資本金の大きな企業の場合もともに利益率が減少する傾向にあることが見て取れる。
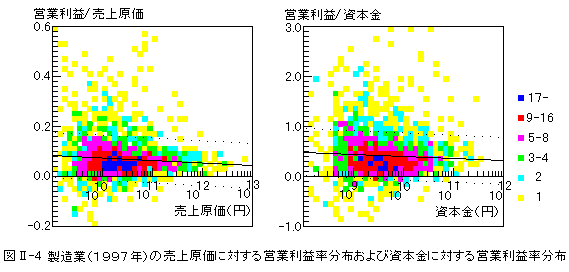
- 企業の営業利益に営業外損益(金融収支など)を加減した経常利益についてみると次のようになっている。
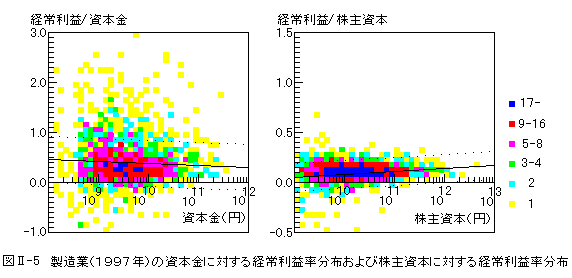
- 資本金に対する分布では右肩下がりであるのに対し、株主資本に対する分布では逆に右肩上がりとなっている。株主資本は純資産または自己資本とも呼ばれているものであるが、それは資本金の他に法定準備金および剰余金を加えたものである。
- 企業活動の目的が利益を求めることであるが、売上高に対する営業利益率が4%程度に押さえられている今日では、営業利益が売上高と売上原価等との引き算の結果としてしか得られないということは、本質的で深刻な問題である。社会の必要を満たすだけ十分な量を生産することから離れて、利益を上げることを目的とした資本主義的生産活動は異常である。
- この異常さを個々の企業に強制しているものについては、次回以降に検討する予定である。
続く